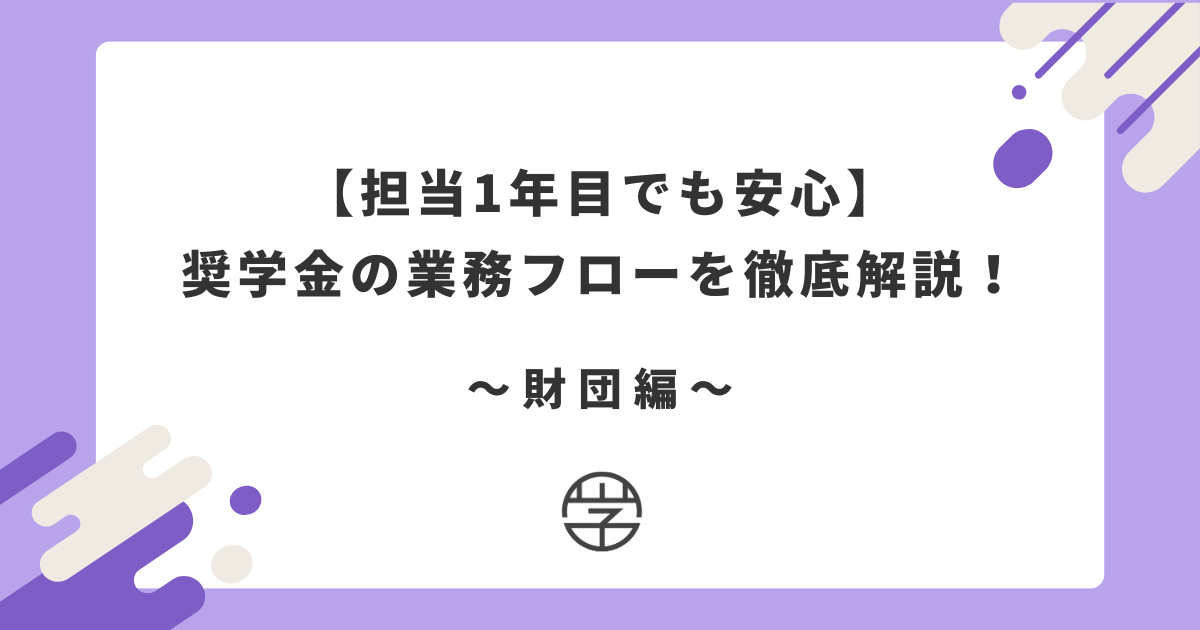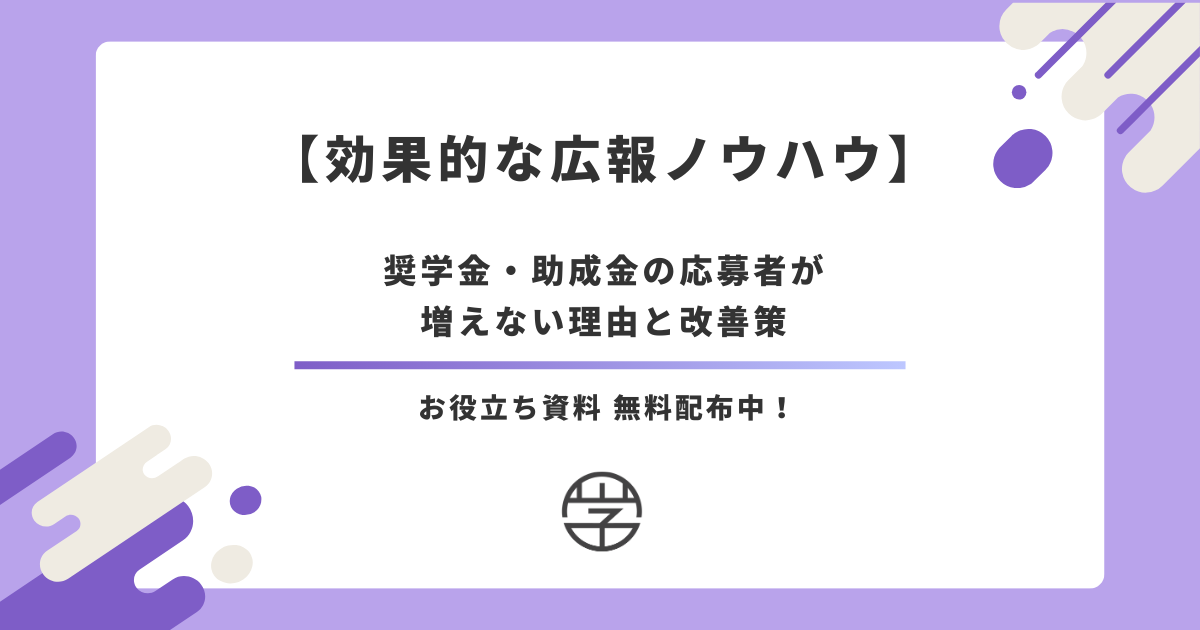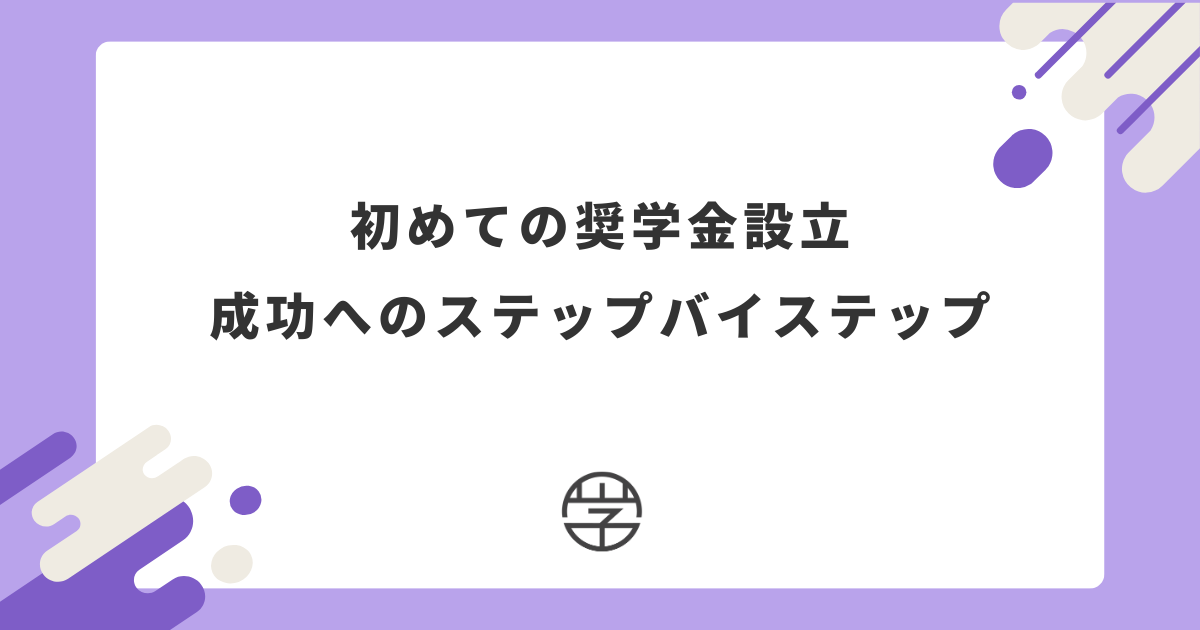
奨学金の立ち上げは、学生支援や地域貢献を目指す団体にとって重要なプロジェクトとなりますが、事業の特性上、初めて担当するという方がほとんどです。初めての担当者でもスムーズ奨学金の立ち上げプロジェクトが進められるよう、具体的な手順をステップごとにまとめました。
運営団体を決める
目的に合った運営組織の選択
奨学金の設立目的に応じて、最適な運営組織を選ぶことが重要です。企業型、一般財団型、公益財団型のいずれかを選び、組織の特性を活かして運営を行いましょう。
| 企業型奨学金 | 企業が自社PRや社会貢献を目的として設立する奨学金です。企業のブランドイメージ向上やCSR活動の一環として活用されます。 |
| 一般財団型奨学金 | 柔軟な運営が可能で、特定の目的や地域に特化した支援が行えます。設立手続きが比較的簡単で、運営の自由度が高いのが特徴です。 |
| 公益財団型奨学金 | 社会的な信頼性が高く、広範な支援が可能です。公益認定を受けることで税制上の優遇措置を受けられるため、寄付金の集まりやすさがメリットです。 |
奨学金を通じて達成したい目的に応じて、最適な組織形態を選びましょう。
奨学金の内容を決める
奨学金設立の核となる部分です。以下の要素が最重要となりますので順に決めていきます。
奨学金の種類
まずは、奨学金の種類を給付型(返済不要)か貸与型(返済が必要、利子の有無も決定)かを決定します。
給付型
学生の負担が減り、社会的なインパクトが大きいですが、長期間の運営にわたっては運営資金の調達が課題となります。
貸与型
返済を必要としますが、利子の有無や返済期間を柔軟に設定することで学生の負担軽減ができます。
対象となる学生
地域、学部、家庭環境など、対象となる学生の条件を設定します。例えば、特定の地域出身の学生や特定の学部に在籍する学生、家庭の経済状況が厳しい学生など、支援対象を明確にすることで状況を把握し、的確な支援ができるようになります。
支給額と支給期間
年間の支給総額(毎月の支給額)や支給人数を決定します。これにより年間のおおよその予算が把握できます。支給額は学費や生活費をカバーできる金額を設定し、支給期間は1年単位や卒業までなど、学生のニーズに合わせて柔軟に設定します。
応募方法と選考プロセス
オンライン応募の導入など利便性を意識した設計が求められます。応募書類の内容や選考基準を明確にし、公平な審査を行うことが重要です。
学生に周知する(奨学金の広報)
奨学金の情報が支援を必要とする学生に届かなければ意味がありません。情報提供の方法を工夫しましょう。
ホームページへの掲載
webサイト上に奨学金の詳細情報や応募方法を分かりやすく掲載し、学生が簡単にアクセスできるようにします。ただし、webサイト上に掲載するだけでは、学生が検索してすぐ情報を見つけられる訳ではないので、検索結果に表示されやすくなるよう、自団体のwebサイト掲載だけでなく、学生の目に触れる機会の多いwebサイトなどに告知をすることもおすすめです。

SNSでの発信
InstagramやX(旧Twitter)など学生がよく利用するSNSを活用し、告知を行います。SNSはwebサイト上の掲載とは異なり、ユーザーの興味関心により、閲覧する情報も異なります。よって、一度きりの配信では、届けたいユーザーへ情報を届けることは難しく、定期的な配信や、奨学金の募集要項以外の情報を配信することも重要です。
学校や教育機関との連携
学校側へメールや郵送物で募集要項を周知してもらうよう案内を出したり、学校と協力して奨学金の説明会を開催し、学生に直接告知を行います。奨学金を実施している他の団体からも案内が届いている学校も多く、学校と連携、コミニケーションが非常に重要になります。
奨学金情報サイトへの掲載
学生がよく閲覧するサイトやSNS、専用プラットフォームを活用し奨学金情報を掲載することで、より多くの学生に情報を届けます。多くの団体様が日本最大級の奨学金検索サイト「ガクシー」に、奨学金情報を掲載し、学生に情報を届けています。

学生の利便性を考慮した設計と広報活動
奨学金の内容や応募方法を学生にとって分かりやすく、利用しやすいものにすることが大切です。また、効果的な広報活動を通じて、奨学金の存在を広く知ってもらうことが必要です。
奨学金を運営する
奨学金の運営には、主に以下のような業務が発生します。それぞれの業務について解説しています。
応募者の学生情報のデータや提出書類の管理
届いた応募者からの提出書類を整理と確認をし、審査員などが閲覧、審査のしやすい状態に整えておく必要があります。また、個人情報保護の観点からも、どの学生の書類かを把握し、管理をしておく必要があります。
応募書類の受付・審査
応募書類を受け付け、選考基準に基づいて審査を行います。公平性を保つために、複数の審査員による評価を行うことが望ましいです。
支給手続きとフォローアップ
奨学金の支給手続きを行い、支給後も学生の状況をフォローアップします。貸与型の場合は返済管理も含まれます。返済計画を学生と共有し、無理のない返済をサポートします。
個人情報を扱うため、管理システムの導入やセキュリティ対策を徹底することが不可欠です。
奨学金の評価と改善
奨学金の運営が始まったら、定期的に評価と改善を行うことが重要です。以下のポイントに注意しましょう。
学生からのフィードバック
奨学金を受けた学生からの意見を収集し、改善点を見つけます。アンケートやインタビューを通じて、学生の声を反映させ、より良い支援ができるように改善をしていきます。
運営コストの見直し
効率的な運営を目指し、コスト削減の方法を検討します。予算の使い方を定期的に見直し、無駄を省きます。これによって募集人数の上限枠を増加させたりできます。
目標達成度の確認
奨学金の目的が達成されているかを定期的に評価する。支援の効果を測定し、必要に応じて運営方針を修正します。
法的手続きと税務対応
奨学金の設立には、法的手続きや税務対応も必要です。以下の点に注意が必要です。
法人格の取得
必要に応じて法人格を取得し、法的な基盤を整えます。法人格を取得することで、社会的な信頼、信用が向上し、寄付金が集まりやすくなります。
税務申告
奨学金の支給に伴う税務申告を適切に行います。税務専門家の助言を受けながら、正確な申告を行います。奨学金などの税務に詳しい専門家に相談をすることをお勧めします。
法的コンプライアンス
個人情報保護法やその他の関連法規を遵守する。法的な問題を未然に防ぐために、コンプライアンスを徹底します。
奨学金の持続可能性
奨学金を長期的に運営するためには、持続可能性を考慮することが重要です。以下の点に注意しましょう。
資金調達
寄付やスポンサーシップを通じて奨学金の運営における安定した資金を確保します。定期的な資金調達イベントなどを開催し、支援者を増やすことも重要です。
運営体制の強化
専門スタッフの育成やボランティアの活用を検討しましょう。運営体制を強化することで、安定した運営が可能になります。また、奨学金の業務経験があるスタッフが見つかると尚良しです。
リスク管理
経済状況の変動や法改正に対応できる体制を整えます。リスク管理計画を策定し、予期せぬ事態に備えておきましょう。以下に、奨学金設立の成功に向けた具体的なポイントをまとめます。
奨学金の設立に向けた具体的なポイント
奨学金の設立は、多くの学生にとって大きな支援となり、社会に貢献する重要なプロジェクトです。改めてポイントをまとめましたので下記を参考にしてください。
【1】運営団体を決める
【2】奨学金の内容を決める
【3】学生に周知する(奨学金の広報)
【4】奨学金を運営する
【5】奨学金の評価と改善をする
【6】法的手続きと税務対応を検討する
【7】奨学金の持続可能性を検討する
このガイドが、奨学金設立の第一歩を踏み出す際の参考になれば幸いです。具体的な設立の手順について本記事の内容を含め奨学金の運営にお役立てできるよう「奨学金立ち上げチェックシート」をご用意しましたので、下記からDLください。